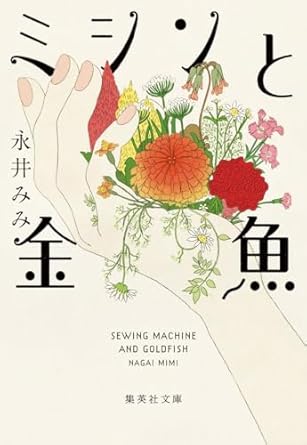出版社直送!きっと読みたくなる、今年の夏文庫
<読者へのメッセージ/文庫読みどころ紹介>
著者による「読者へのメッセージ」あるいは書評家・評論家による「文庫読みどころ紹介」を掲載。今夏注目の文庫本をご紹介します。
角川文庫
温かな日常に潜む疑惑
相いれない二つの感覚の「同居」が物語を駆動させる
荒岸 来穂
『残像』はサスペンスが原動力である犯罪小説というジャンルの中でも、ほかの作品にはあまり見られない力学が、物語を駆動している。
主人公である浪人生の堀部一平は何事にも身が入らない空虚な日々を過ごしていた。ある日、バイト先で倒れた同僚の老人・葛城直之を彼の住むアパート「ひこばえ荘」まで送ったところ、葛城の隣の部屋に住む女性たち、晴子・夏樹・多恵の三人と出会う。一平は成り行きで葛城のために三人が用意していた誕生パーティーに参加するものの、別れ際に晴子から「二度と来てはだめ」と忠告される。
しかし、一平は再び葛城がバイト先で倒れたため、「ひこばえ荘」にまた足を運ぶこととなり、その後も様々な事情でこのアパートを訪ねることになる。アパートを何度も訪ねるうちに、年も性格も違う三人がどうして同居しているのか好奇心が湧いてくる一平。ある日、彼女ら三人と共に暮らす(が三人の誰とも血縁でないという)小学生の男の子、冬馬から、彼女ら三人が全員前科持ちであると聞かされる。彼女らが同居しているのはなぜか、なぜ二度とここに来るなと忠告されたのか、何かを企んでいるのだろうか……。一平は疑問に思いながらも彼女らとバーベキューをしたり動物園へ出かけたりと親交を深めていく。それが彼女らの「計画」の一環であることも知らずに……。
共同生活の目的、秘められた彼女らの過去、何かしらの計画の予感。一平と彼女らの物語とは別に語られる、もう一人の視点人物である吉田恭一のエピソードはどう絡んでくるのか……。本書はサスペンス小説らしく「謎」には事足らない。しかし、こんなにも謎めいた設定がちりばめられているにもかかわらず、読者が読むこととなる物語は、主人公と彼女ら、そして葛城を取り巻くどこかハートフルな日常の一場面が大半を占めている。
いや、だからこそこの物語はサスペンスフルなのである。こんなに温かな日々なのに、彼女らの抱えた秘密ゆえに、一平が経験する微笑ましいエピソードを読者は心穏やかなまま享受することはできない。出来事の裏には何かが仕組まれているのではないかと常に疑いながら、ページをめくることとなるのである。青春小説の趣すらある一平と彼女らの毎日がいつひっくり返るのか。読者は期待と不安がない交ぜになった感情を味わうこととなるだろう。
前科がある女性三人による共同生活という設定の奇妙さと、彼女らと過ごす何気ない日々の温かさ、この相いれなさそうな二つの感覚がまさに「同居」することでサスペンスが生まれる。サスペンスを生むのは、目を背けたくなるような暴力的な犯罪や、息もつかせぬスリリングな展開だけではないのだ。温かな日常に潜む疑惑とそれがもたらす不思議と穏やかなカタルシスは、読後に感傷的な気分を残していく。
強烈な光そのものではなく、余韻のように残る「残像」、この言葉ほど本作の読後感を表すのにふさわしい言葉はないかもしれない。(あれきし・らいほ=ミステリ批評)
光文社文庫
生きることは、失うこと
過去の思い出、大切な人との別れをテーマに
高橋由太
近く刊行される『ちびねこ亭の思い出ごはん 茶トラ猫とたんぽぽコーヒー』はシリーズ九作目、私にとって最長のシリーズとなります。これまでにないほどの執筆意欲を維持している希有の作品と言えるのかもしれません。
今までの作品ですと、シリーズが続くとネタ切れに悩まされることが多かったのですが、『ちびねこ亭の思い出ごはん』シリーズはネタ切れを起こすことなく、実際のところ、現時点でもあと五冊分くらいのアイディアのストックがあります。その上、書きたい内容は日々増えています。「書かなければならない」と使命感を覚えることさえあります。
どうして執筆意欲が衰えず、しかもネタ切れを起こさないのか。私なりに考えました。
故郷の千葉県君津市を舞台にしているということもあるのでしょうが、おそらく私の年齢によるものが大きいのではないかと思います。この『ちびねこ亭の思い出ごはん』はそのタイトル通り、過去の思い出が題材であり、大切な人との別れがテーマになっています。
この作品を書き始めたときには、実家に両親がいて、弟が二人いました。やがて父が死に、母が他界し、弟までこの世を去っていきました。五人家族が、私ともう一人の弟の二人になってしまいました。
また、同級生やお世話になった編集者でも、私の前から去っていく方が増えました。昔からテレビなどで見ていた芸能人が鬼籍に入るニュースを頻繁に目にするようになりました。誰もがこの世を通りすぎていき、自分だけ取り残された気持ちになるときがあります。
生きることは、失うこと。
失うことは、生きること。
繰り返しシリーズの作中に登場する言葉です。それを実感しながら、『ちびねこ亭の思い出ごはん』を書いています。
また、次の一節も作品(『たび猫とあの日の唐揚げ』)からの引用ですが、こんなことを書いています。
生きることは、一人旅をすることなのかもしれない。誰かと出会っても、いずれ別れなければならない。だからこそ、二人でいる時間が愛しい。
二人で旅していた記憶を、あるいは一人旅の記憶を、こうして『ちびねこ亭の思い出ごはん』という小説の形で残そうとしているのかもしれません。辛くて悲しい、けれど幸せな旅が続くかぎり、きっと書くことはなくならないのではないでしょうか。
これからも、登場人物たちのさまざまな思い出や、彼らが作り出す温かい料理の数々を描き続けていきたいと思います。そして、その物語が読者の皆様の心に少しでも寄り添うものになれば幸いです。
『ちびねこ亭の思い出ごはん』を手に取っていただいた皆様の旅のお供になれるよう、これからも作品を書いていきたいと思っております。(たかはし・ゆた=小説家)
集英社文庫
広い世界の片隅で
巡り合った『優しさ』を伝えたくて……
永井 みみ
合鍵を使ってシャッターを開けると、目の前に彼女が倒れていました。私は動転し、彼女の名前を呼び、肩に手を掛けました。
彼女はすでに、つめたく、かたく、なっていました。
ヘルパーになって、ひと月。私にとって彼女は、初めて担当したご利用者でした。彼女にとっても私は、初めてのヘルパーでした。初回訪問の自己紹介では、お互いとても緊張していました。同行した責任者は「急な仕事が入った」と言い、生活支援で行える清掃の範囲、手順、物品の置き場所を説明し、慌ただしく退出しました。二人きりで取り残され、彼女は照れて「えへへ」と笑いました。「他人を家に入れたくなかったんだけど、椎間板ヘルニアが酷くなって屈めなくなっちゃったから、仕方なく訪問介護をお願いしたの」そこまで喋ってもう一度、彼女は「えへへ」と笑いました。「ヘルパーがあなただってわかってたら、もっと早く来てもらうんだった」
一階は手前の半分が元店舗の土間、奥が居室になっていました。駅から離れたこの地で、長年彼女は揚げ物や手作りサラダなども扱う精肉店を一人で営んでいました。「ずっと商売をしてたから、会った瞬間気が合うかどうかがわかる」と、彼女は言いました。私は掃除をしながら彼女の身の上話を聞きました。結婚して、二年で離婚したこと。その後一念発起して、現金でこの店舗兼住宅を建てたこと。親族はいるにはいるが、事情があって音信不通になっていること。車の運転が得意だったこと。などなど。掃除が終わり書類を書いていると、彼女は「帰りにちょっと二階を覗いてみて。時間が無かったら、いいけど……」と、遠慮がちに言いました。
二階に上がり、私は「あっ」と声を上げました。
そこはまるで、小さなミュージアムでした。
壁には所狭しとポスターが貼られ、ガラスの陳列棚には公演プログラムやブロマイド、サイン色紙、額縁入りツーショット写真、紙吹雪の詰まったオルゴール、チケットの半券等々が綺麗に並べられていました。すべて、SKD(松竹歌劇団)関連のものでした。
「すごいですね」と私が言うと、彼女は「亭主そっちのけで日本じゅうどころか世界じゅう追っかけて行ったから。ある日帰って来たら、目ぼしい家具を持って亭主は逃げちゃってた」と言い、「でもぜんぜん後悔してないの」とつづけ、「えへへ」と笑いました。
その後、訪問する度に彼女は「もっと良い仕事があるはずだから、職安行ってみたら?」と、心配顔でアドバイスをくれました。
救急車を待つ間、何もできず私は彼女の名前を呼びつづけました。
彼女の顔は穏やかで、微笑んでいるようにも見えました。
主人公のカケイさんにとってみっちゃんがたくさんいるように、私にとってのカケイさんも一人ではありません。世界の片隅で出会った優しさを伝えたくて、『ミシンと金魚』を書きました。(ながい・みみ=作家)
新潮文庫
断片という純粋な結晶
理解からはみ出すわからなさのたまらない魅力
頭木 弘樹
「フランツ・カフカのどの作品がいちばん好きですか?」と問われることがある。
最初の出合いは『変身』だったから、やっぱり特別な思い入れがある。「ある朝、ベッドの中で虫になっていた」という出だしは今も衝撃的だ。三つの長編小説も好きだ。十代の少年がアメリカに行く『アメリカ』、何もしていないのに逮捕される『審判』、どうしても城にたどりつけない『城』。短編小説も好きだ。父親から死刑判決を受ける『判決』、不思議な処刑機械の出てくる『流刑地にて』、食べたいのに食べられない『断食芸人』などなど。けっきょく全部好きなわけだが、それでも特にと選ぶなら、日記、手紙、断片が好きだ。
日記や手紙の言葉を中心に『絶望名人カフカの人生論』(新潮文庫)をカフカ没後九〇年に出してもらえた。そして今年、カフカ没後一〇〇年で、『カフカ断片集』を出してもらえた(『決定版カフカ短編集』の編者も務めた)。
断片というのは、短い、未完成な、小説のかけらだ。花瓶のかけらを見せられて、「いい花瓶でしょ!」と言われても困ってしまう。花も生けられない。だから、普通はかけらより完成品のほうがいい。しかし、カフカの場合は特別なのだ。カフカの断片には、完成した作品にはない、独特の魅力がある。たんに書きかけとかメモとかもあるだろうが、多くの場合、断片というかたちでしか書けないものを書いている。彫刻家のロダンのように、あえて未完成な作品を創る芸術家もいる。カフカの場合はわざとではないが、完成品にするために、自分が必要ないと思うことを書き足したり、辻褄を合わせたりすることができないのだ。こうしか書けないという切実さ、混じりけのなさが、独特の輝きを生んでいる。いったん断片に魅せられると、完成品でなければとは思わなくなる。
ただ、全集なら断片も収録されてきたが、文庫で断片だけで一冊にというのは初めてのことだ。読者に受け入れてもらえるのか、じつのところ心配だった。「短編集」ならわかるが、「断片集」では何のことかわかりにくい。わざわざ断片から読もうとする人も少ないかもしれない。
もうひとつの大きな問題は、断片は決してわかりやすくはないということだ。カフカは簡単な言葉しか使わないし、文章も平易だし、「これは自分のことだ!」と共感できるところも多い。しかし、その一方で、つねに理解からはみ出す。よくわからないところが残る。そこがまた、たまらない魅力なのだが、はたして「わかりやすさ」が求められる今の時代に、「よくわからないけど、なんだか面白い!」ということを楽しんでもらえるのかどうか……。
ところが、実際には刊行後すぐに重版になり、発売から一カ月半で五刷まで重ねることができた。カフカのすごさをあらためて感じると同時に、読者を信頼して出版して本当によかったと、しみじみ思っている。(かしらぎ・ひろき=文学紹介者)
中公文庫
創作活動=「わがままな所業」
魂の自由への欲望が私たちの心を射抜く
和合 亮一
石垣りんの詩の魅力。簡潔で、豊かで、ユニークで、時に苦みがあって。優しさもあれば、厳しさもあり、貧しさがあれば、贅沢さも伝わってくる詩の一つ一つ。戦争と戦後の経済成長を生きた激動の時代が、平易で明快なまなざしで写し出される印象を持つだろう。今回のエッセイ集を読み耽りその味わいをあらためて覚えた。女性として、勤め人として、詩人として、地に足をつけて生きた石垣への親しみが、文章からより深く湧いてきた。
エッセイはⅠ「はたらく」、Ⅱ「ひとりで暮らす」、Ⅲ「詩を書く」、Ⅳ「齢を重ねる」の四つのキーワードでまとめられている。ⅠからⅣの流れは、そのまま石垣の人生を描き出している。戦後の荒廃からの復興が強く叫ばれた時代に、上の学校へは行かずに銀行員の道を選ぶ。給料をもらいながら好きな勉強(=創作活動)をこつこつしたいという理由からである。その志の通りに熱心に文芸雑誌への投稿をし続ける。
働きながら詩作と向き合った石垣の日本社会と家へのまなざしが文章から良く伝わってくる。「家庭には家庭のしがらみ、職場には職場の忍従。たくさんのがまんで成り立っている日々の暮しの中で、たったひとつ、どうしてもしたかったこと」。昭和を生き抜きながら、皆に愛される詩を産み出してきた理由の一つはここにあると分かった。「詩でさえ、それが制約であるなら、とらわれないようにしたいものだ、と思っています」。
創作活動とは「わがままな所業」とも同じ文章で述べているが、例えば令和に生きて詩作=わがままとは誰が思うだろう。昭和の空気が持つ「しがらみ」や「忍従」が現代では良い意味でほどけつつあるとあらためて知る。籠のようなものに囲われてしまう日常を貫こうとする矢が、独特のユーモアとアイロニーの詩と文章の筆致のなかに放物線を描くようにしてしなやかに放たれていると感じた。魂の自由への欲望が時代を超えて私たちの心を射抜く。
独身を貫き職業人として家計を支えてきた。五〇歳の時に実家を出て、退職金でローンを完済できる見込みで1DKのマンションを購入。初めての一人暮らし。それを描いた佳品がⅡからは特に多い。様々な心と言葉というものの形がいろいろな器に盛られて差し出されているかのようだ。単に一人で生きるという風景がそこに描写されているのではない。生きることの真理ひいては書くことの真実に、そのまま繫がっていく感じがある。
「私が住んでいるアパートの三階と並行の高さで、少しはなれた土手の上を、私鉄の電車が横一文字に走っている」。都会の喧噪の象徴とも言うべき光景である。「ひとり暮らしの私には、それがにぎわいになっている」と。定年まで働き終えて退職。やがて生活だけが残されていく。寂しがりも楽しみもしながら、いつも眼の前に詩を置く。言葉というものを奪われない領分として生き抜こうとする姿を見た。「私にとって詩は自身との語らい」。(わごう・りょういち=詩人)
文春文庫
ずっと色褪せない小説
僕らの〝いま・ここ〟の原風景を映し出す
長瀬 海
〈この世があまりにもカラフルだから、ぼくらはいつも迷ってる。/どれがほんとの色だかわからなくて。/どれが自分の色だかわからなくて〉。
『カラフル』は森絵都が一九九八年に発表した不朽の名作で、最新の奥付を見ると七十二刷(!)と書かれてる。現代文学は、それが〝いま・ここ〟を描くものである限り、時間の経過とともに物語に滲んだインクが色褪せる宿命を背負わずにはいられない。でも、この作品はいつ読んでも僕たちの〝いま〟を描いた小説だという感じをうける。なんで『カラフル』はこんなにもずっとカラフルなんだろう。
小林真。十四歳。美術部に所属し、絵を描くのが大好きな少年が、ある日、自殺を遂げた。そんな彼のからだに〈ぼく〉の魂が降臨するところから物語ははじまる。
〈ぼく〉は下界であやまちを犯し、死んでしまったらしい。それが何か、自分が何者かわからない彼の目の前に、天使があらわれた。プラプラと名乗る天使は〈ぼく〉に命ずる。輪廻転生するために再度、下界で修行を積んでこい、と。
プラプラの指示で真のからだを借り、再挑戦することになった〈ぼく〉。期間は一年。真になりきりながら彼の家族のもとで生活を送る〈ぼく〉はいきなり真を苦悶させた原因に直面する。それは、私欲に塗れた人間の醜い姿だった。
習い事先の講師と不倫をする母親。出世のことしか頭にない父親。頭の悪い真をせせら笑う、意地悪な兄。〈ぼく〉は健全とは言えない家庭に嫌悪感を抱く。さらに、真が思いを寄せる女子が中年男性と交際していること、それから、そんな彼に手を差し伸べてくれる友人が誰もいないことを知って愕然とする。
あまりに息苦しく、救いのない世界。色のない真の絶望は、経年劣化すらも拒むほどにキツい。孤独の深淵を覗いたこの小説は、そこにある残酷な風景から目を逸らさず、一人の少年の苦しみを生々しく描く……だけじゃなく、その世界が再び色を取り戻す瞬間を鮮やかに活写するのだ。苦しみの底から少年を救い出す希望の輝きだって経年劣化することはない。それはいつの時代も僕たちに世界を生き抜く勇気を与えてくれる。不安だらけの世のなかでも、明日に期待していい理由を教えてくれるんだ。
といった感想をひっくり返すようだけど、いま、本作を読むとここに平成の精神性が刻印されていることにも気づく。援助交際。スニーカー狩り。父親は底抜けの不況のなかで働いてるし、母親は自分探し(これも平成のキーワード)に勤しんでいる。真も、〈ぼく〉も、平成の空気に窒息していて、そこで喘ぐ二人の声はあのとき以来、社会で何がおかしくなったのかを示している。〈もともとぼくには平成なんてむいてないんだよ〉。そんな少年の言葉は、いまも過去の残響となることはない。
令和時代の『カラフル』再読は、あの日から閉塞感が地続きであることを知るきっかけにもなるだろう。色褪せない小説は、僕らの〝いま・ここ〟の原風景を映し出してもいたんだ。(ながせ・かい=書評家)
河出文庫
その声…
「まことの花」を開かせた世阿弥との不可思議な縁
藤沢 周
――それはわが父、観阿弥の形見……。
仏堂の中空から聞こえてきた、その声からすべては始まったのです。
『風姿花伝』や『花鏡』などの芸能論は読んでいたとはいえ、その著者である世阿弥について書こうなどという大それたことは、その時までつゆとも思っておりませんでした。
現代人の心の闇や狂気を描いていた自分が、なにゆえ室町時代に能を芸術として大成し、幽玄の美で都じゅうを瞠目させた天才能役者・世阿弥を書くことになったのか。その不可思議な縁は、世阿弥が永享六年(一四三四)に七二歳の身で咎なく佐渡島に流され、逗留した正法寺なる禅刹で、その声を聞いた一夜があったからなのです。
新潟市の漁師町に生まれ育った私は、毎日のように海辺から優美な島影を眺めておりましたから、佐渡は馴染みの島ではあったのです。子どもの頃はキャンプや釣りや海水浴などレジャーでしか行っておりませんでしたが、やがて、その地にある正法寺に室町時代の美の造形者が晩年住んでいたのを知ることになりました。そして、佐渡の人々が能を残してくれた世阿弥を偲んで、毎年六月にその本堂で「ろうそく能」を行っていることも。
それから毎年正法寺に伺い、本堂の結界に灯されたろうそくの幽けき炎と、そこから浮かび上がってくる昔日の霊の物語を見、また世阿弥が所持していた「雨乞いの面」という寺宝の神事面を拝ませてもらっていたのです。黒く煤けて古びた面は、べしみのように目を見開き、口を大きく結んだ瞋恚の色。ですが、おそらくは万象の邪気を払うがために力を込めた表情なのでしょう。
ある時、その面をぼんやりと見ていた時に、堂の天蓋のあたりから、「それはわが父、観阿弥の形見……」という、世阿弥の声が降りてきたのでした。その刹那、「雨乞いの面」を神妙にかける世阿弥の横顔と、さらにその姿を見守る影が見えたのです。突然、自分の中で、「書ける! 書かねば!」と打たれたような想いになって、一気に書き上げたのが『世阿弥最後の花』なのです。
老いという人生の鄙の地、佐渡という都から遠く離れた鄙の地。これは現代においても生老病死という意味では変わりません。いかに生きていくか。いかに自らを立てていくか。すべてを失ってもなお、自らの「花」=美を極めようとした世阿弥のあり方は、今こそ私たちに光を与えてくれるものと思います。
世阿弥は晩年、佐渡の神秘的な大自然の力と村人たちとの豊かな交わりの中から、「まことの花」を開かせたのではないかと今でも信じています。また、真の意味での他力を尊重し、敬うことを作者自身が知ることになったのも、世阿弥とその声のおかげだと思っております。(ふじさわ・しゅう=作家)
祥伝社文庫
次は、お前かもしれないぞ。
呪いの人形が主役のハートフルコメディ
藤崎 翔
週刊読書人をお読みの皆様こんにちは。本日は、今年二月に祥伝社文庫より発売された僕の作品『お梅は呪いたい』をご紹介します。
この小説は、戦国時代以来の封印を解かれた呪いの日本人形「お梅」が、現代人を次々に呪い殺す……つもりだったのに、約五百年のブランクが長すぎて、間違えて現代人を次々に幸せにしてしまうという物語です。呪いの人形が主役の物語史上、最もハートフルなコメディです。逆にハートフルコメディ史上、最も「呪」「殺」という漢字が出てきます。
さて、実は僕がこの小説を書いたきっかけになったのが、作家仲間のSから、着物姿の女の子を模した不気味な日本人形をもらったことだったのです。
なんでもその人形は、元々はホラー作家のAさんが譲り受けたのだそうです。しかしAさんは、ある日突然失踪してしまい、その人形を次に引き取ることになったミステリー作家のBさんも、突然筆を折った末にやはり失踪してしまった。その後も、その人形を所有した作家が次々と廃業、失踪してしまったらしく、それが手元に回ってきてしまったSは、ひどく怯えた様子でした。
でも僕は、幽霊やオカルトなど全然信じないタイプの人間なので「いいよ、俺がもらってやる」と、その人形を快く引き取りました。そして、その人形からインスピレーションを得て『お梅は呪いたい』を執筆しました。ありがたいことに『お梅は呪いたい』はたくさん増刷もしてもらえました。僕は筆を折るどころか、むしろ絶好調なのです。
まあ、薄々予感していたことですが、やっぱりこの人形の噂はただのデタラメでした。だいたい怪談なんてものは古今東西、全部人間の創作に決まってるんですから、本物の幽霊や呪物なんてものは存在するわけないんです。今も僕の部屋にある、こんな小汚い人形のせいで、大の大人の作家が筆を折るとか失踪するとか、そんな馬鹿なことが起きるわけないんですとか書かれたらさすがに私も黙っているわけにはいかないな。
私を恐れるどころか、私を題材に小説を書くなど、ずいぶん度胸がある奴だと感心していたが、私を愚弄するとは言語道断。さすがに堪忍袋の緒が切れた。残念ながらこいつもここまでだ。
こいつの体は乗っ取った。もうこいつ自身の意識が戻ることはない。近いうちに、過去の持ち主たちと同じようにこの体を操り、人里離れた山中にでも捨て、人形としての私は、新しい持ち主を探すとしよう。
週刊読書人をお読みの諸君、貴重なものを読んだな。藤崎翔という一人の作家の命が終わる瞬間だ。といっても、いわゆる作家生命ではなく、本当の命が終わる瞬間だ。
次の私の持ち主は、お前になるかもしれないぞ。
(編集部注)こんな原稿が送られてきたきり、藤崎翔さんに電話をかけても全然つながらず、部屋を訪れても無人なのですが……まあ、これも藤崎さん流の冗談だろうし、たまたま出かけてるだけに決まってます! うん、そうに決まってます!
(ふじさき・しょう=作家)
東京創元社の文庫
少年たちの罪と罰
一生終わらない初恋の物語
弥生 小夜子
二人の少年にとって聖域といえる図書室はほの暗く、彼らだけが透き通る光に包まれています。主人公の立原志史がどこかあどけなさを残していることから、出会ってまもない頃であるのがうかがわれます。志史のやわらかな微笑みは、作者の私が「よかったね、こんなに幸せなひとときがあったんだね」と語りかけずにはいられないほどです。もう一人の重要人物である小暮理都が後ろ姿であることには意味があり、繊細なタイトルデザインは風に揺れる前髪を思わせ……表紙の素晴らしさだけで字数が尽きてしまうのでこのへんにしますが、この場をお借りして単行本の装幀・装画についても謝辞を述べさせてください。初めて単行本を手に取ったとき、デビュー作をこんなにも美しい本にしていただけたという感激で言葉になりませんでした。本当にありがとうございます。
さて、本作のタイトルは物語の核となる理都の短歌「風よ僕らの前髪を吹きぬけてメタセコイアの梢を鳴らせ」からとっています。作中で理都がつづった十首の短歌は彼の心情を偽りなく映したものですが、文庫化にあたり、それぞれへの志史による返歌をつくりました。
たとえば「てのひらをかたみに置きて肋骨の内心臓は咲き誇るかな」には「おたがいの心臓としてとりかえたビーカーに咲く球根の花」という歌を。ギリシャ神話には花に変わる少年が登場します。アドニスはアネモネに。ヒュアキントスはヒヤシンスに。いずれもが球根を持つ花であることは象徴的で、志史の歌も同じアナロジーを内包しています。
「光りつつ降る花びらを浴びながらあの角までは俤と歩む」の俤は弟の文字を含むことからも誰を指すか明白で、志史は「生まれくる前の僕らの魂が呼びあうように舞う花吹雪」と返すのです。
本格ミステリの砦である鮎川哲也賞で優秀賞をいただいた本作ですが、必ずしも「本格」とはいいきれないであろうことをお断りしておかねばなりません。ミステリであると同時に少年たちの「罪と罰、そして一生終わらない初恋の物語」なのです。
ミステリとしての主眼は「なぜ」を追うこと、何より志史の心の謎を解き明かしていくことにあります。一つの殺人事件の調査を進めるにつれて過去のいくつもの事件が浮かび上がり、探偵役の若林悠紀は彼らをとりまく闇の深さに立ちすくむことになるのです。ある後悔を抱える悠紀は同じあやまちを繰り返すまいとして、手遅れと知りながらも精一杯志史によりそおうとします。それが徐々に届いて、会うごとに志史は一枚一枚鎧を脱ぎ捨てていくのです。
彼らが守ろうとしたもの。手に入れようとした夢。そのために何を実行したのか。すべてが明かされたときそこにいる本当の志史に会ってくださったらうれしいです。けがれない少年だった頃のままの志史に。(やよい・さよこ=作家)