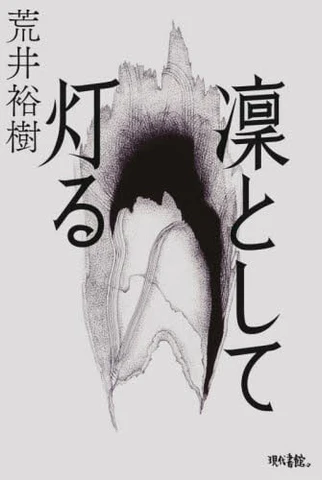本書はウーマン・リブの運動家の米津知子の評伝である。
一九七四年四月二〇日に東京国立博物館で開催された『モナ・リザ展』は乳幼児を連れた人や付き添いの必要な人の入館を断っていた。公開初日、展示会場で「身障者を締め出すな」と抗議を叫び『モナ・リザ』に赤いスプレーを噴射した知子が警察へ連行されるという事件が起きる。
この事件を主軸として学生運動、ウーマン・リブ、障害者運動といった様々な社会運動が地続きであることを示しながら、彼女の半生を回想する形式で進んでいく。
びっしりと手書きされた長文のビラが随所に挿入されている点が魅力的だ。リブのビラに書かれる言葉は、男性が主体であった全共闘の生硬な用語とは異なる。それは意図的に肉声を強調し書かれたものであり、女たちが自分を曝して真剣にぶつかっていくような印象を受けるとともに、当時の運動の温度感を感じた。「届け」「伝われ」という切実な願いと、「目を逸らすな」「女も、障害者も生きさせろ」という悲痛な叫びが入り乱れているようだ。「欲望の畑にクワを入れろ」といった一見すると扇動的な表現から、「ありのままのあなた」と出会うためにそれを書く者も「ありのまま」を曝しているのだと、著者は当時の生の言葉を端緒として文字列では読み切れない裏側を映し出していく。
リブ合宿後、『婦人公論』に寄せた手記の中で、知子は自問する。
ざまあみろ、とうとうやった。しかし、誰に向ってざまあ見ろなのだろう?
「自分を救うためには、自分を壊すしかなかった。」と書かれるように、葛藤しながら自身を見つめて生き抜いてきた知子の心情を丹念な筆致で拾い上げ、「世の中の不合理」や「権力への反抗」といった大きな物語に包摂されがちな、個人の生きた足跡を残している点に読みごたえがある。
「どの女性の身に起きたことも、決して他人事では済まなかった。」と語る米津はリブ新宿センターにおいて、機関誌の発行、家出・暴力・妊娠・中絶・避妊などの女性のための各種相談、デモや集会の企画運営など多岐にわたる活動を行う。
こうした二四時間三六五日、生活即運動といった壮絶な時間を「皆、小さな火花を見つけて集まってきたんです」「やっと会えたから大事にしたかった」と本書の刊行記念イベントで米津本人によって振り返られていたのが印象的であった。
本書のあとがきで著者の荒井氏は「私には無理だろう」と「私にしか書けないだろう」の狭間で揺らぎながら一文字ずつ積み上げたと語っている。それはどんな感じなのだろうか。
書くとは自分と向き合うことなのだと思う。
世界でたった一人、たった一つのことを書くこと。
しかし、それを通じて誰かと繫がることができるということ。
本書は、現代において取り零されやすい個人の存在を文学で掬い取るという挑戦に果敢に臨んでいる。
著者はこうとしか言えない表現で「心の在処」を証明し続けている。
★はつしば・りほ=二松学舎大学文学研究科博士前期課程二年。ゴッホが好き。夏休み、新宿のSOMPO美術館で「ひまわり」を見てきた。とても優しい感じだった。絵は自分でも描く。休日は絵画教室で油絵を習い、青い絵を描いている。