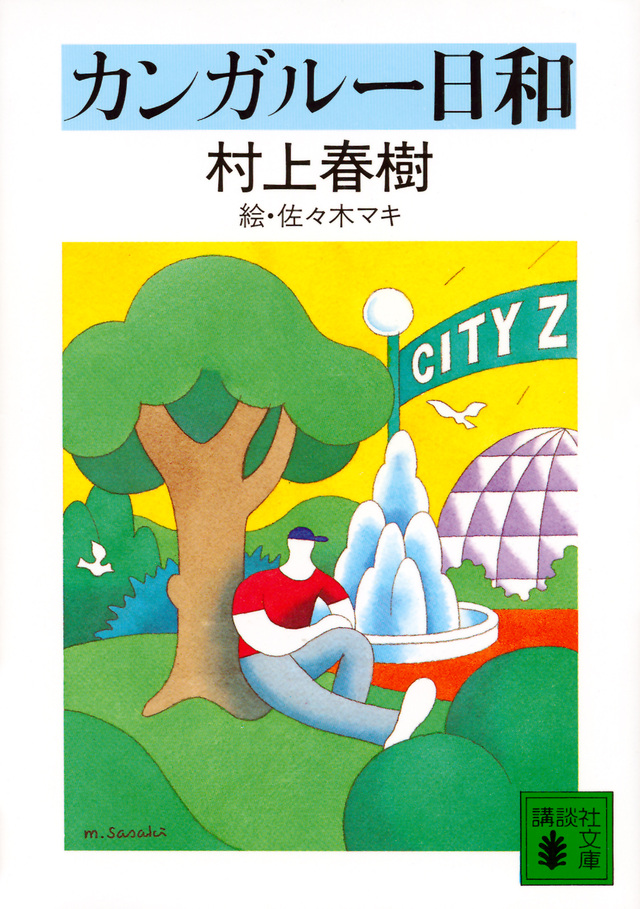本書に収められた18の短篇は、どれも不思議な雰囲気を醸しつつ、同時に自分の身近で起きそうな、もしくは既に起きていそうな日常を感じさせる。私たち読者は1篇1篇読み進める度に、現実と非現実の絶妙な混ざり具合に惹きつけられる。
本書は例えば、家賃が安い、線路の間の三角地帯に住む夫婦の生活を書いた「チーズ・ケーキのような形をした僕の貧乏」、一年間毎日スパゲティーを茹で続ける男の孤独を書いた「スパゲティーの年に」など、「日常」の何気ない時間に詰まっている面白さに気が付ける作品集だ、と思う。いろいろな人のいろいろな人生の一部を垣間見、いろいろな「今」を旅した気持ちになる。今回は18個の中から3つのおすすめの作品を紹介する。
まずは表題作の「カンガルー日和」。「日和」は晴れたいい天気のことで、「○○日和」は○○をするに相応しい日であることを意味する。行楽日和などと使われるが、「カンガルー日和」とは? この物語に登場するカップルは「一ヵ月間、カンガルーの赤ん坊を見物するに相応しい朝の到来を待ち続けていた」。その日を待ち続け、やっと「我々は朝の六時に目覚め、窓のカーテンを開け、それがカンガルー日和であることを一瞬のうちに確認した」時には、カンガルーの赤ん坊は「もう赤ん坊じゃないみたい」に成長していた。しかし二人にとって、それはいい日になりそうだった。そもそも「相応しい」とは誰が決めるのだろうか。私はこの作品に、「日和」は誰かに決められるものではないというメッセージがあると思う。スケジュールに追われる毎日をふと見つめ直したくなった。
2つ目は「4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて」だ。この物語ではある男が自分にとって100パーセントの、運命の女の子を見つけ彼女と話してみたいと願い、告白の科白を考える。しかし考えてみたところで女の子とはすでにすれ違っていてどんなに考えてもこの思いを伝えることは叶わず、「僕は彼女にそんな風に切り出してみるべきであったのだ」と思い返すしかできない。それにしても長い告白の科白だ。作品ほぼ丸ごと全てが、男のストーリー仕立ての告白なのである。はっきり言ってこんな告白をする男は厄介ではないだろうか。しかしチャンスを不意にした時こそ、アイデアが湧いてくるものかもしれないと思う。
そして最後に短編集のラストを飾る「図書館奇譚」を紹介する。これは本を探しに来た少年が地下室に案内され、なんと一ヵ月の間、監禁されて分厚い本を丸暗記させられたあげく、知識が詰まった脳みそを吸われると告げられる。その後、彼はその牢屋からの脱出に成功するものの、日常に戻った後も「いったいどこまでが本当に起こったことなのか、僕にはわからない」と、図書館に行くことが出来なくなってしまう。私は、彼が図書館から遠のいてしまったのは、間違った読書法でトラウマを抱えたからだと思う。それは言うまでもなく「知識を詰め込むための読書」だ。知識を補うことだけが読書ではないと確信させられた。本は知識の宝庫であることは間違いないが、愉快な気持ちになったり不思議な気持ちになったり感情を動かされる本に出会うことこそが大切なのではないだろうか。本書は、そんなふうに様々な感情をもたせてくれる作品である。
★たちはら・ありあ=共立女子大学国際学部3年。海外のニュースが日本では拡散されにくい状況に疑問を持ち、留学で知り合った友人たちと世界中のニュースを日本で拡散し疑問を投げかける学生マガジン発行を目指し活動しています。