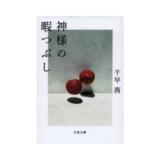響く銃声、溢れる無辜の民衆の血、まるで捨てられた人形のように扱われる死体……。現代のK-POPアイドルがみせる煌びやかな韓国のイメージとはあまりにかけ離れていて、若い世代には想像するのが難しいかもしれないが、本書に描写されるのは約40年前の韓国の現実なのだ。
1980年5月18日、韓国全羅南道の道庁所在地だった光州において、軍事政権に対して民主化を要求する市民と軍とが衝突した。軍は市民のデモを徹底的に暴力によって押さえつけたが、この出来事は韓国が民主化していく上での起爆点となった。
『少年が来る』は、この光州事件にまつわる六章の物語から成る長編小説である。第一章「幼い鳥」では、少年トンホが友人のチョンデと彼の姉を探すために遺体安置所である尚武館を訪れ、そこで出会ったチンス兄さんやウンスク姉さんを手伝って、軍に殺された人々の遺体の納棺を記録する。「君」ことトンホは年の割に華奢で周囲に心配されるが、戒厳軍がやってくるからここに居たら死ぬぞ、と言われてもなお、危険を顧みずチョンデを探すことを諦めない。
しかし、第二章「黒い吐息」でトンホの願いが河清であったことが明かされる。この章の語り手は死後の魂としてのチョンデだからだ。弔われることなく軍人にぞんざいに扱われ腐敗していく遺体は、かつて生きていた、人間だった頃の姿からどんどん遠ざかっていく。にも関わらず、遊離している魂の語りは、まだ生命が途絶えていないような鮮やかさをもっている。
第三章以降では、1980年から数年、あるいは数十年経った後の物語が展開される。第三章「七つのビンタ」は、軍事政権下で検閲対象の本の編集を担当したキム・ウンスクが、検閲課から受けたビンタを忘却していく物語だ。第四章「鉄と血」では、軍に逮捕された「私」とキム・チンスが受ける拷問が描かれる。光州事件以後にも、軍人による暴力が終わることはなかった。
第五章「夜の瞳」、第六章「花が咲いている方に」は、それぞれイム・ソンジュ、トンホの母が語り手となる。1980年5月を生き延びてしまったが故の苦しみと絶望が、語り手に刻み込まれていて無くならない。トンホは彼らの心の中で生き続けている。トンホの母は小声でそっと呼びかける。「……ねえトンホ」。「トンホ」という言葉に伴う、えもいわれぬ重く悲しい響きは章を追うごとに増幅され、第六章の母の声によって窮まる。
著者のハン・ガンは光州で生まれ9歳まで過ごし、光州事件の数ヶ月前に偶然にもソウルに移っていた。彼女もまた、生き残った1人として苦しみを背負っている。エピローグはそうした視点から語られる。
そして、それは光州事件を経験していない読者、日本では戦争を経験していない読者に、過去の暴力を知ることができている著者自身が、もうその暴力の跡も表面的には目立たない、平和な世界に生きていることを気づかせるのである。現在と断絶したものとして過去の暴力を眺めるのではない。過去の人々が受けた痛みを、現在の平和な状況でどのように受け止めるのかを、トンホを軸とした「小さな物語」は読者に突きつけているように思われる。
正直、この本を読み進めるのは苦しい。しかし、著者も苦しみを抱えている。彼女が苦しみに向き合う誠意は、この世のものとは思えない深い絶望にも、まっすぐ降りていくことを可能にしている。あなたも彼女と一緒なら、深く、深く降りていくことができると信じている。(井手 俊作訳)
★かまた・せいけん=東京大学前期教養学部2年。
街の書店で開催される、文学作品を読む読書会に参加しています。学生は私だけですが、大人の方々との議論がとても刺激的で楽しいです。