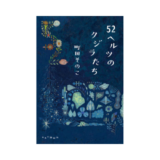社会人三年目を迎えた伸行は、少し余裕も出来てまあまあの日々を過ごすなか、あるライトノベルのことをふと頭によぎらせる。中学生の頃に読んでラストが受け止めきれなかった作品だ。「俺以外の奴は、あのラストをどう受け止めてたんだろう?」十年以上前の作品だ、いまさら馬鹿馬鹿しいと思いながら、伸行はインターネットで感想を検索する。そして、ブログ「レインツリーの国」と、その管理人のひとみに出会う。ひとみの言葉と感性に触れた伸行は、ハンドルネームを「伸」として、衝動的に彼女に宛ててメールを送る。
こんなきっかけで伸とひとみの交流は進んでいく。互いにライトノベルの感想を書き合うふたりはとても楽しそうだ。メール越しのふたりのテンポ感は絶妙で、読んでいるこちらも気持ちが良い。そんなやり取りからは、ふたりがその本に対してどれだけの熱量を持っているのかがわかる。考察合戦を繰り広げる彼らはまるで同志のようで、自分が注いだ情熱の分だけ、相手からも同量またはそれ以上の熱さが返ってくるようなかけがえのない存在に思えた。そして、その唯一無二感が彼らの関係を変化させる。はやくひとみに返信したい、たとえ会社の飲み会を途中で抜けてでも。そんな風に思う相手に好意を抱いていないわけがない。またひとみも伸とのやり取りに心地良さを感じており、予想どおりふたりは惹かれ合う。だが、ここからが問題なのだ。
「青春菌」まみれの恥ずかしい言葉の応酬を繰り広げたのち、伸は切り出す。
「なあ、一回勝負してみんか? 会って話してみん? 顔合わせて、いつもどおり恥ずかしい会話を平常心で出来たほうが勝ち。面白そうやない?」
こんなに居心地の良い相手に会ってみたくない人間が果たしてこの世にいるのだろうか。しかしこちらの期待をよそに、ひとみからの返事は「史上最長の五日間」空く。
作品を読み進めていくと、ひとみが想像以上に面倒くさい性格の持ち主であることがわかる。それは彼女のもともとの性質に加えて、抱えた傷に起因するものだ。伸がひとみの傷を理解しようとすればするほど、「どうせわかるはずがない」と言わんばかりに、「自分しか傷ついたことがない」顔で、ひとみは伸の気持ちを突っぱねる。そのせいで、ウェブ上でうまくいっていたふたりは、会うたびに衝突してしまう。はじめ私はなぜひとみがそのような態度を取るのかわからなかったが、当の本人もまたわかっていなかった。作者はそれを、ひとみ自身に気付かせる形で書き上げているが、その理由を知った時、胸がちくりと痛む。ひとみは自分が抱える特別な傷を盾にして伸を傷つけていたからだ。しかも、伸が持つ「完全に理解の範疇を越える」傷によってそれに気づかされる。だが、そんな自分を思い知るのはきっと彼女ばかりではない。誰しも皆、大なり小なり傷を負っていてその痛みを知っているはずなのに、他人もまた同じように傷をもっていることを忘れてしまう。どんなに小さくても、痛みを一番感じるのは自分の傷だからだ。自分が痛いとき、私たちはどれだけ他人を慮れるだろうか。そうした人間というものの複雑さに、伸に気づかされ、ひとみと一緒に向き合える物語である。
村井ひかり / 獨協大学外国語学部ドイツ語学科2年
★むらい・ひかり=獨協大学外国語学部ドイツ語学科2年。サウンドトラックまたは劇伴と呼ばれる音楽に関心があり、現在は『必殺仕事人』で知られている、「必殺シリーズ」というテレビドラマの劇伴を研究しています。