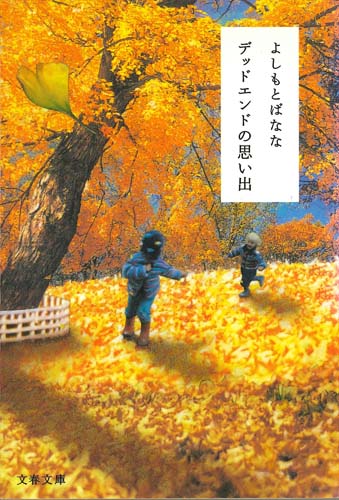私たちが生きる現代は目まぐるしい。情報が社会を駆け巡り、欲していない情報までもが耳に入ってくる。そんな社会で生活をしていると、息が詰まるようなときがある。そのような状況に陥ったら、短編集『デッドエンドの思い出』を読んでほしい。この作品集は、心の休憩所である。
本書には5編が収録されるが、どの作品の登場人物も、特別に強かったり、社会的な立場を持っていたりする人ではない。そして、彼女らが経験することも、私たちが絶対に経験しないとは言い切れないものばかりである。「あり得る非日常」とでも言えばいいのだろうか。そんな「あり得る非日常」を送るなかで、登場人物の誰もがぬくもりを求めていた。
「幽霊の家」の「私」は、八年以上の時間をかけて本当に自分が必要としていた関係に気づいた。その相手は岩倉くんと言った。彼と出会ったときには、ときめきがなく、恋人にはならないだろうと「私」は思った。けれど、「私」と岩倉くんには共通点が多いこと、岩倉くんの纏う雰囲気が安らかであったことが、時間をともにしたいという気持ちにはさせた。老夫婦のような落ち着いた時間を彼とは過ごせた。
「幽霊の家」における「あり得る非日常」は、岩倉くんの住むアパートに大家夫婦の幽霊が出ることである。その幽霊たちは普通に生活を送っているのだった。「私」は、その姿を見ながら、大家夫婦の関係性を想像したり、幽霊を見守ってしまう岩倉くんの人の好さに思いを馳せたりする。そうして岩倉くんのことを考え、時間を共有するにつれ、「私」は彼に惹かれていく。
のちに「私」は、あの大家夫婦の幽霊がいなければ、「私」たちは結ばれなかったのではないかと語っている。そして、思うのである。いつか「私」たちも、あの幽霊夫婦のように消えてなくなるのだろうが、誰しも同じ流れのなかにいるのだ、と。
この作品集の共通点は、三つあると私は思う。これまででふたつは述べた。ひとつは「あり得る非日常」、もうひとつが「誰かとのぬくもり」である。最後の共通点は、「私たちが生きる世界を大きく捉えること」である。「幽霊の家」の「私」が語ったように、どの作品の登場人物もこの世界の大きさを知っている。
たとえば、「「おかあさーん!」」の「私」である。彼女は、母親のDVから逃れるため、父方の祖父母のもとで育った。「私」は、ある日、勤め先の社員食堂で大量の風邪薬が混入したカレーを食べ、体調を崩す。大量の風邪薬は、だるく精神的に辛い毎日を彼女に送らせた。
そんな苦しい状況下で彼女を救ったのは、窓から入ってくる清々しい夜風だった。ふと、少しでも状況が違えば、カレーに風邪薬を入れた人や自分を捨てた母親と、笑い合えていたかもしれない、そんな世界もどこかにあるかもしれないと「私」は思う。
この作品集は、登場人物たちがはっきりとした光を見出す物語ではない。希望に満ちた物語とは言えないだろう。けれど、報われるのかわからない日々のなかで、時空を超えた流れや、あり得た日常に思い至った彼女らの語りは、ふっと肩の力が抜けるような、安らぐ感覚を与えてくれるにちがいない。読後は、この世界が少しだけ明るく見えるはずである。
小淵康平 / 上智大学理工学部2年
★おぶち・こうへい=上智大学理工学部2年。高校時代から読書好きに。以来、男性作家の作品を好んで読むが、最近では女性作家の作品にも挑戦中。本を片手に喫茶店へ行ったり、散歩したりするのが趣味。