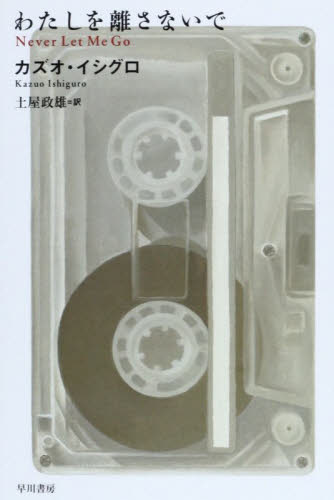これまで私は、身体を端緒として人間を観察したことがあっただろうか。人間という存在は当たり前のものすぎて、日常のなかに埋没してしまっていたように思われる。私はいまこうして文章を構成しているが、この命を、ふと手に触れた髪の毛一本一本を、おぞましいものだと考えたこともなければ、大きく脈打つ心臓やキーボードで文字を入力していく手が、「わたし」とは異なるものとして感じられる、ということもない。現在は退屈で、時が無限に続くように思われ、故に過去に遡らなくては、自分の存在そのものさえ信じられなくなってしまうことがある。しかし本当は、人生とは泡沫だ。生きていく、とは平原に生えた唯一本の木が途方もなく風を受け続けることに似ているのではないか。12月の寒空に浮かんだこの心象が私を『わたしを離さないで』という物語へ導いた。
これはヘールシャムという、深い森林に覆われた学舎風の施設で子ども時代を過ごし、必至の「使命」を遂行する短い生涯が、三人の若者を軸として描かれていく物語だ。閉ざされた施設内で、絵画を鑑賞する、図画工作を行うといった情操教育を受けてきた彼らは、指針通りにごく普通の恋愛や言い争いをし、物事に触れ、心を動かされ、思考し、成長していく。
彼等は小さい頃から、それとなく使命を仄めかされるのだが、それでも友人と馬鹿みたいに笑い転げたり、音楽を聞いて身体がリズムを取ったり、異性に対する衝動を感じながら生を連続させてきた。そしてその先には自身に課された使命、すなわち必然とされた「提供」による死が用意されている。生産された存在だから、という理由で私たちと同じように感情を持ちながら生きてきた人間が、初めから生など授かっていなかったかの如く処分されるのだ。彼等の晩年は病室で、崇高な使命のために空疎となった身体を横たわらせ、励ます仲間や介護士とともに最終の使命までの命を数えて過ごす。訪れた使命終了日、名残惜しむ間も与えられず、純白の手術台の上に載せられる。それは幼い頃に手に入れた宝物や仲間の存在、終わりかけの恋愛、いま心臓に脈打たれているこの身体も、全てが死へと引き裂かれてしまう瞬間だ。最期まで手をしっかり握り応援する介護士もまた、ある日突然来る使命開始を告げる通知からは逃れられない。
この物語を読み終わった私には、運命に抗えない身体から発せられる叫び声が絶えず闇で木霊し続けるように感じられた。分断された命は、何に託すことができるだろう。身体から溢れ出す感情と咆哮。定められた運命、虚無の向こうに死が待つなかで生きようとするときに、思い出が人間を灯す光となるのか。いや、生きるとは血の奥から発せられる生々しい肉声を指す言葉なのではないか。
散歩帰りによる町外れの公園。思い立ってブランコを漕ぎ、焦点を一点に定めふとこんなことを思った。敷地を囲う落葉樹は、今年も変わらず夏に枝一杯の葉を茂らせることだろう。緑に、緑に、逞しく輝いてほしいと思った。(土屋政雄訳)
★かとう・えま=愛知淑徳大学文学部2年。大学生活を通して色々なことに挑戦をしようと考えています。最近ではミスジャパン2021に応募し、Youtubeにも動画を上げましたので、宜しければ応援ください。