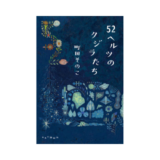「ここでまず断っておきたいのだけれど、これは僕の恋愛に関する物語だ。その恋愛に、共産主義やら民主主義やら資本主義やら平和主義やら一点豪華主義やら菜食主義やら、とにかく、一切の『主義』は関わってこない。念のため」
物語はこのように始まる。
主人公「杉原」は、不良が多く通う男子校の生徒だ。中学までは在日朝鮮人として民族教育を受けていたが、国籍を韓国に変え、日本の高校に通い始める。元ボクサーの父親にならい、「在日」に向けられた差別や偏見に対しては、徹底的に力で応戦してきた。
杉原は高校の友人の誕生会で、桜井という女子に声をかけられ、恋に落ちる。在日であることを隠しつつ、毎週末デートを重ね、桜井の家族にも紹介される。桜井との仲を深める中で「在日」としてのアイデンティティを意識せざるを得ない事件が起きる。民族学校からの親友が、地下鉄で刺殺されたのだ。杉原は、親友の死をきっかけにして、桜井に自分が在日だったことを告白する。桜井は困惑し、韓国や中国の血が汚いと言う父親の口癖を思い出し、杉原を受け入れることができなかった。しばらく連絡が途絶えたあとのクリスマスイブの晩、桜井は杉原を呼び出す。国籍や出自の事実はどうやっても変わらないし、社会に深く根付いた差別意識もすぐにはなくならない。それを十二分に味わった二人なりの結論を出す。
私がこの小説をお薦めする理由は、次の3つだ。
まず、読みなおすたびに、日本社会で差別や偏見を受ける「杉原」や彼の友人、家族のような人たちの想いを直視することだ。理不尽な扱いに対する悔しさ、やるせなさをバネにした、強い反骨心や野心に魅了される。
そして、その想いを理解するための土台として、これまで学校で学んだことや、ニュースでなんとなしに言われていることを、フル活用する必要があること。おそらく私は、在日と呼ばれる人たちの気持ちを完全に理解することは不可能で、学んだ知識をもとに想像することしかできない。学校での勉強の意味を実感するとともに、小説の助けを借りて想像することの大事さも知った。
さらに本書を読むことで、「私は日本で生まれ育った日本人なんだなあ」ということを自覚できる。それは、私が恋愛や将来について話すとき、冒頭の杉原のような、「お断り」をした思い出がないことからも明白だ。
私が初めて本書を読んだ中学三年のとき、この小説の背景を理解することができなかった。「在日朝鮮人と在日韓国人って何か違うの?」「日本に韓国人が住んでいて当たり前じゃないの?」などと疑問が湧いて、人物関係や登場人物たちの気持ちに想いを馳せるどころではなかった。「恋愛小説って言ったくせに、恋愛がメインじゃないのか」と期待を裏切られた気さえしていた。
その後、高校の世界史の試験前に、朝鮮戦争を勉強する息抜きとして再読した。中学生の時の疑問は理解できるようになってきたものの、「在日」という人種問題が日本に存在しているということが、どうしてもリアルに感じられなかった。
再々トライしたきっかけは、大学一年でたまたま履修した、さまざまな差別問題を扱う講義だ。「在日」問題が今も根深いことを知った。やっと、この物語に出てくる言葉や熱情の息遣いを感じられた気がした。それでも「在日」問題を、日常的に意識する場面は少ないが、桜井のように、好きになった人が「在日」だという状況もあり得る。
自分が桜井だったら――まだまだ私には、胸を張って「それでも自分の思いを貫き通せます」と言える勇気はない。だからこそ何度でもこの本を読み直して、考え続けることを忘れないでいたい。
★なか・しおり=上智大学外国語学部3年。
美味しいパンを見つけることにハマっています。