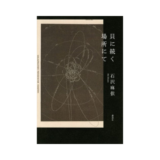日本文化を分析対象にしたこの本は、アメリカ情報局の依頼により、第二次世界大戦時に文化人類学者のルース・ベネディクトにより執筆された。
本書は、敵国として、占領国として、全く違う二つの立場に置かれた日本について、アメリカ人が見た様々な矛盾や疑問を不可解と切り捨てず、更に古い時代に遡り材料を集め、古来から不変の日本的価値体系を探り出す。戦中・戦後に見られた日本人の独自性、例えば特有の宗教観や天皇観、反抗と恭順の切り替えの早さなどは、当時の米国人にとって理解し難いものであった。著者はそれに対し、庶民の生活の常識や、近世の風習などを資料として加え日本人の特徴を見つけていく。
「生活の諸要素や各人の立場の『領域』を分け、その場に応じて態度を変える臨機応変さ」、「行動においては『善悪』や『損得』以上に『恥』に敏感」、「西洋の言葉では定義しづらい『義理』という概念」等々、様々な性質を発見し、日本人の一見矛盾した行動を論理づけていく。日本人の目から見ても、普段意識しない自国特有の思考の枠組みを、客観的に考える新鮮な機会となるはずだ。
また、著者の繊細かつ自信のある筆致にも注目したい。
本書全体を通して、著者は極めて繊細に言葉を選んでいる印象を受ける。それは「敵国」というデリケートなものを扱う意識からか、中立的な目で文化を研究することの実践からか、著者は実状に対して過剰な言葉を用いたり、単純な批判や賞賛の言葉で論理を結論づけたりしない。常に事実に対し論理的で等身大の表現を用い、また違う視点で見た際の反論を意識し、それが予見できた場合は自分の理論との整合性を説明する手間を惜しまない。この点は本書の信頼性が憑拠するところの一つでもある。
一方で、著者は要所では確固たる表現を用いる。例えば著者は当時のアメリカ人が持つ日本に対する一般論を「素人じみた」考えだと批判し、自分の意見を主張するにあたっては、広義に解釈する余地のない、強い確信のある言葉を使っている。時に現れる、こうした明らかに強調された表現は、著者の自身の文化人類学者としての誇りの意図せぬ表出のようにも思える。
学問書として完成しながら、著者の学者としての生き生きとした自信、人間らしさが伺えるのも本書の魅力の一つだ。
戦時故に現地調査が不可能な状況でありながら、後世においても一定の信頼を得て読み継がれる本書は、コロナ禍でなかなか現地に赴けない今日の研究環境にとっての明るい示唆ともなり得、ともすると陥ってしまう研究への諦観を牽制する一冊でもある。現代、学問を志す若輩にとって、自分に届いた先の時代からの贈り物と称してもよいものであり、その堂々たる筆致は、共感と示範を与えてくれる檄となることは間違いない。(角田安正訳)
※プロフィールは応募時のもの。筆者は四月現在、大学を卒業している。
★おざき・じゅんぺい=明治大学農学部食料環境政策学科4年。
趣味は読書と旅行。最近は、夢野久作や宮沢賢治など、地方出身者による小説をよく読んでいる。